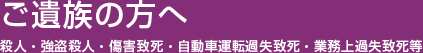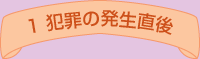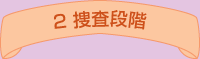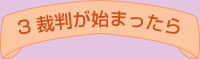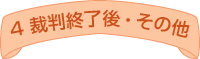精神的にとても苦しい
警察の指定被害者支援要員や、検察の被害者支援員が、民間被害者支援団体や外部のカウンセラー等を紹介、引き継ぎします。また、自助グループ(犯罪被害に遭われた方やご遺族の方々の団体)も紹介します。
マスコミが来て困っています
警察や弁護士が間に立ち、ご遺族の方の心情を代わりにマスコミに伝え、できるだけ直接マスコミが来ないようにすることができます(弁護士には仕事として依頼することになりますので、有料です)。
今後の手続を知りたい
警察の指定被害者支援要員が刑事手続の説明をします。
また、本HPの「全体の流れ図」もご参照下さい。
一人で証言台に立つ又はビデオリンクの別室で証言するのは不安
裁判所が相当と認めれば、親族の方や、心理カウンセラーなどが付添人となり、その方があなたのすぐ近くにいる状態で証言することができます。検察官に相談してみてください。
意見陳述制度があります。
→法廷において、被害者の方にご自身の心情や意見を述べてもらう制度です。希望される方は、検察官にお申し出下さい。
平成20年12月1日以降に起訴された事件が対象です。
- 被害者参加制度があります。
被害者参加人としてご本人又は代理人たる弁護士が裁判に参加することができます。
被害者参加人になると、
①公判期日への出席
②検察官の権限行使に対して意見を述べ、説明を受ける
③証人への情状面での質問
④被告人への質問(情状面に限られない)
⑤弁論としての意見陳述(どの位の刑が相当と考えるか) ができます。
参加を希望される方は、検察官に申請をして下さい。
(ただし、裁判所が、被告人または弁護人の意見を聞き、犯罪の性質や被告人との関係その他の事情を考慮して、参加が相当であると認めたときに、参加の許可決定をすることになっており、必ず参加できるとは限りません。また、各々の手続について検察官に対する申請、裁判所の許可決定が必要です。)。
- 被害者参加人の方のための国選弁護制度があります(法テラス)。
ご本人自身が参加するのではなく、弁護士を代理人として参加する場合、国選の被害者参加弁護士を選定請求することができます。ただし。以下の資力要件があります。
(要件を満たさない方は、ご自身のご負担で弁護士と契約することになります。)
資力要件:現金、預金等の流動資産の合計額から、犯罪行為を原因として3月以内に支出することと認められる費用の額を控除した額が150万円未満の方
この制度の利用をご希望される方は、下記法テラスのページをご参照下さい。
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/trouble_ichiran/20081127_3.html
裁判がどうなったのか知りたい
判決書を含む確定記録を閲覧することができます。裁判所にお申し出下さい。
加害者がその後どうなったのか知りたい
検察の被害者等通知制度を利用して、被告人の出所予定日・実際に釈放された段階では釈放の事実と釈放年月日の通知を受けられます。通知を希望する方は、担当の検察官や被害者支援員にお伝え下さい。
経済的問題(お金の問題)について
加害者に対する賠償請求
加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
加害者が任意に支払わない場合は、通常民事訴訟を提起して請求していくことになりますが、刑事裁判を活用する下記の方法を利用することもできます。
- 刑事和解制度の活用
裁判外で和解(示談)が成立した場合、事件を審理している刑事裁判所にその旨を申し立てると、公判調書にその合意内容を記載してもらうことができます。
これにより、被告人が示談の約束を守らずお金を払わない場合に、別途民事訴訟を提起して支払請求する必要はなく、当該刑事裁判の公判調書を利用して、強制執行の手続をすることができます。
-
損害賠償命令制度の活用(過失による致死事件〔自動車運転過失致死・業務上過失致死〕
はこの制度の対象となりません。)
平成20年12月1日以降に起訴された事件が対象です。
刑事裁判所に対して、被告人に対する損害賠償請求の申立て(申立て手数料2000円)をすると、刑事事件の有罪判決の後、同じ裁判所が刑事訴訟記録を取り調べ、原則4回以内の審理により、(被告人に賠償責任があると判断されれば)損害賠償命令が出されます。
これにより、通常の民事訴訟を提起するより、時間的にも金銭的にも(通常の民事訴訟提起には請求する額に応じた印紙代が必要)負担が軽くなります。
ただし、損害賠償命令に対して被告人が異議申立てをした場合は、通常の民事裁判所で審理することになります。
国に対する給付金請求
犯罪によりご家族を亡くされた方は、犯罪被害給付金制度を利用できます。
①地元の警察署又は警察本部で申請書を記入し、②各都道府県の公安委員会に申請することになります。③公安委員会の裁定を経て支給裁定がされると、支給裁定通知が届きます。④給付金支払い請求書に記入して提出すると、⑤口座振替又は送金払いで給付金が受領できます。
NPOの方にお願いすると、申請の補助をしてくれます。
具体的な金額については、申請の申込をする警察や申請を補助して下さるNPOの方にご相談下さい。
ご参考
遺族給付金の額:320万円〜2964万5000円
(被害者の方の年齢や勤労による収入額に基づいて算定されます)
給付金の支給対象者:
①配偶者
被害者の収入で生計を維持していた被害者の②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
上記以外の⑦子、⑧父母、⑨孫、⑩祖父母、⑪兄弟姉妹
このうち第1順位の遺族の方が遺族給付金の支給を受けられます。
被害者の弁護士費用に関する扶助制度の利用(法テラス)